忍者と殺し屋。
本来なら出会ってはいけないふたりが、ひとつ屋根の下で始める奇妙で優しい同居生活。
『忍者と殺し屋のふたりぐらし』は、そんな“ありえない関係性”のなかに、ほんのりと百合の香りと、命のやりとりを超える日常の温もりを描いた異色の物語です。
原作は2021年から連載中の人気コミック、アニメは2025年4月から放送がスタートし、その“ギャップ萌え”と“情緒のある演出”がSNSでも話題を集めています。
この記事では、原作とアニメの違いを踏まえつつ、物語のテーマやキャラクターの関係性、そして多くの視聴者が感じている「尊さ」や「百合的魅力」について、感情を交えて深掘りしていきます。
忍者と殺し屋が選んだ“日常”とは、果たしてどんなものだったのか?
あなたも一緒に、ふたりの静かで不思議な暮らしを覗いてみませんか。
- 『忍者と殺し屋のふたりぐらし』の原作・アニメの基本情報
- 原作とアニメの演出やキャラ描写の違い
- ふたりの関係性に宿る百合的魅力と感情の深さ
TVアニメ『忍者と殺し屋のふたりぐらし』、好評放送&配信中!
忍者と殺し屋が、まさかの“同棲生活”!?
殺伐プロフェッショナルの、のんびり癒し系コメディ!放送:各局にて2025年春クールより放送中
配信:Amazonプライムビデオほかにて随時配信中!
- 30日間の無料体験で今すぐ視聴OK!
- 好きな時間に、好きなデバイスで!
- 映画・音楽・マンガも一緒に楽しめる!
原作とアニメ、それぞれのあらすじ紹介
これは、戦うことしか知らなかった忍者と、殺すことしかしてこなかった殺し屋が、
――一緒に“暮らす”ことを選んだ、ちょっと不思議で、すごく優しい物語。
草隠さとこは、任務から逃げ出した抜け忍。
生きる意味も、行くあてもなく街に倒れた彼女を拾ったのが、女子高生であり、プロの殺し屋・古賀このはでした。
このはは、容赦なくターゲットを仕留める“殺しの天才”だけど、掃除も洗濯も料理も壊滅的。
さとこは、誰にも頼れず生きてきたくノ一だけど、人の役に立つことには、ちょっとだけ誇りを持っている。
そんなふたりが、一緒に暮らすようになったら?
仕事で“人を殺す”このはと、その死体を忍術で葉っぱに変えるさとこの共同作業。
突拍子もない設定なのに、ページをめくるたびにじんわり沁みてくるのは、「誰かと暮らすことって、悪くないかも」っていう、胸の奥がほころぶ感情です。
原作はハンバーガー先生による漫画で、ギャグと切なさ、過去と現在が絶妙に混じり合ったスタイル。
一話ごとにふたりの関係が少しずつ変化し、セリフにならない“想い”が増えていくのがたまらなくエモい。
そしてアニメ。2025年4月から放送が始まり、映像表現に定評のあるシャフトが手がけたことで、まさかの神作画×エモ空気。
なお、アニメ版ではさとこが街で行き倒れていたところを、このはが拾うというシーンから始まります。
そこへすぐに里からの追っ手が現れますが、このはが圧倒的な強さで返り討ちにし、ふたりの危険な共同生活が静かに幕を開けます。
制作はシャフト、監督は宮本幸裕氏、シリーズ構成は東冨耶子氏、キャラクターデザインは潮月一也氏が担当。
主題歌には、オープニングテーマに「やれんの?エンドレス」(花澤香菜)、エンディングには「にんころダンス」(HoneyWorks feat.ハコニワリリィ)が使用され、作品のユニークな世界観を彩っています。
光と影、呼吸と沈黙、目の動き――そのすべてが、ふたりの“言えない気持ち”を代弁しているかのようです。
アニメは原作の空気を守りつつも、演出面で独自の「深み」を追加。
まるで日常の中に潜む静かな戦いと、どこまでも優しい共犯関係を描いているようで、観ているこちらが何度も胸をつかまれる。
原作が“日々の断片”を切り取る漫画なら、アニメは“心の機微”をすくいあげる詩のよう。
どちらも、ふたりの関係性に、きっとあなたの“何か”が重なるはずです。
原作とアニメの違いを比較|テンポ・演出・キャラ描写の違い
同じ「ふたりぐらし」を描いていても、原作とアニメでは“感じ方”がまったく違う。
それは単なる表現手段の違いではなく、作品に触れる私たちの“心の揺れ方”にまで関わってくるほど、繊細で大きな違いです。
まずテンポ感。
原作漫画はテンポが早く、一話ごとの“オチ”がしっかりあるコメディ寄り。
短いページ数の中で、さとことこのはの距離感がじわっと変わっていく様子が、日常の中にサクサク紛れ込んでいく。
一方アニメは、“間”をすごく大切にしている。
言葉を交わさない沈黙の時間、無言の視線、部屋に満ちる生活音。
そういう“何も起きていないように見える瞬間”が、ふたりの心の奥を深く揺らしてくる。
演出面では、原作がモノローグやコマ割りで表現していた感情を、アニメは「余白」と「音」で見せてくる。
たとえば、さとこの手が皿を洗う動作のリズム、殺しから帰ってきたこのはが一言もしゃべらずにふすまを閉める所作。
その一つ一つが、感情を喋らずに伝えてくるのです。
キャラ描写にも違いがあります。
原作のこのはは、ちょっと子供っぽくて天然な殺し屋。
それがアニメでは、どこか“虚無”を感じさせる静けさと、暴力の痕跡を滲ませるリアルな少女に仕上がっている。
一見無表情なのに、ふとした瞬間だけ「さとこが好き」って心の声が漏れているようで、刺さる人には深く刺さる。
逆に、さとこは原作よりも少し「女性らしく」「儚げに」描かれています。
けれどその中に、誰かを守りたいという強さが確かに宿っていて、ただの“受け”では終わらない芯のある存在になっている。
テンポの良さで楽しめる原作。
感情の揺れで深く浸れるアニメ。
どちらにも魅力があり、どちらから入っても、ふたりの関係性に惹き込まれていくはずです。
百合的魅力と感情描写|“ふたりぐらし”が描く心の距離
『忍者と殺し屋のふたりぐらし』を語るとき、欠かせないのが“百合的魅力”。
だけどこの作品がすごいのは、単に「女の子同士の仲良し」や「距離の近さ」ではなく、“心の距離が変化していく過程”を、ものすごく丁寧に描いているところなんです。
ふたりは最初、あくまで「必要だから一緒にいる」だけ。
このはにとってさとこは“後始末の便利屋”であり、さとこにとってこのはは“居候先の恩人”。
でも、日々を重ねていくうちに、その関係は少しずつ、「特別な誰か」へと変わっていきます。
たとえば、ご飯を作るさとこを、無言で見つめるこのは。
熱を出して倒れたこのはの手を、ためらいながらも握るさとこ。
それは恋とも違う、友情とも言い切れない、けれど確実に“あなたじゃなきゃダメ”な気持ち。
百合って、言葉ではなく“空気”で語られることが多いけれど、この作品ほど「間」が雄弁に語る物語はそうそうありません。
「好き」なんて一度も言ってないのに、ページをめくるたびに、このはがどれだけさとこに依存してるかが伝わってきて、読んでるこっちの心が痛くなる。
そしてアニメでは、その“空気の圧”がさらに強調されます。
小さな音、揺れるカーテン、重ならない足音……そうした演出すべてが、「ふたりの世界だけが、静かに閉じている」ことを示している。
百合が好きな人はもちろん、誰かとの関係に“言葉にできない感情”を抱いたことがある人なら、必ず胸を打たれる作品です。
この作品が教えてくれるのは、恋じゃなくても愛はあるということ。
名前をつけられなくても、大切な感情は確かに存在するということ。
それが、この“ふたりぐらし”が描く、いちばんリアルな百合なのかもしれません。
まとめ:殺しと日常のあいだに咲いた、ふたりだけの物語
忍者と殺し屋。
普通なら交わることのないふたりが、ひとつ屋根の下で“暮らす”という選択をしたとき、
そこには、戦いや任務では決して見つけられなかった、「誰かのために生きる」という感情が芽生え始めました。
生きることが不器用なふたり。
でも、不器用だからこそ、手を差し出すときも、何かを受け取るときも、そこには誤魔化しのない“本音”がある。
その本音が静かに重なって、やがて日常という形を作っていく──そんな愛の形が、この物語には確かに描かれています。
アクション、コメディ、百合、日常。
いろんなジャンルにまたがる本作だけれど、最終的に胸に残るのは、「あなたがそばにいてくれてよかった」という、たったひとつの感情。
『忍者と殺し屋のふたりぐらし』は、命の重さも、誰かと生きる苦しさも、ぜんぶ抱えながら、
それでも“今日”を積み重ねていくふたりの物語です。
そしてきっと、私たちの毎日もまた、誰かとの関係の中で、少しずつ形を変えながら続いていく「ふたりぐらし」なのかもしれません。
- 抜け忍と殺し屋が織りなす共同生活の物語
- 原作はコメディ重視、アニメは感情描写に重きを置く
- “言葉にならない想い”を丁寧に描いた百合的関係性
- 作品の魅力は日常と非日常の絶妙なバランスにある
- アニメ制作はシャフト、主題歌も話題に
TVアニメ『忍者と殺し屋のふたりぐらし』、絶賛放送&配信中!
「クールな忍者 × 無口な殺し屋」
人知れず命をかけるふたりが、まさかの同居生活!?殺伐とした職業なのに、なぜかほのぼの。
笑えて癒される、ゆるアサシン系ホームコメディ。◆TV放送・配信情報
- 2025年春クールより地上波にて放送中!
- Amazonプライム・ビデオなどのVODサービスにて随時配信中!
Amazonプライムで『忍者と殺し屋のふたりぐらし』をチェック
不器用だけど最高なふたりの毎日を、今すぐ追いかけよう!
Amazonプライム・ビデオは月額600円でアニメ・映画・ドラマが見放題!
初回30日間無料体験付きで、気軽にスタートできます。ほのぼの×アクション×同居ラブ(?)の組み合わせはクセになる!
今季の癒しと笑いをお届けする一作です。今すぐAmazonプライムで無料体験
●Amazonプライムの特典
- Prime Video:アニメ・映画・ドラマが見放題
- Prime Music:音楽も1億曲以上聴き放題
- Prime Reading:電子書籍・マンガも楽しめる
- 配送特典:お急ぎ便・日時指定が無料!
『忍者と殺し屋のふたりぐらし』で、クスッと笑える“日常”をあなたの元に。

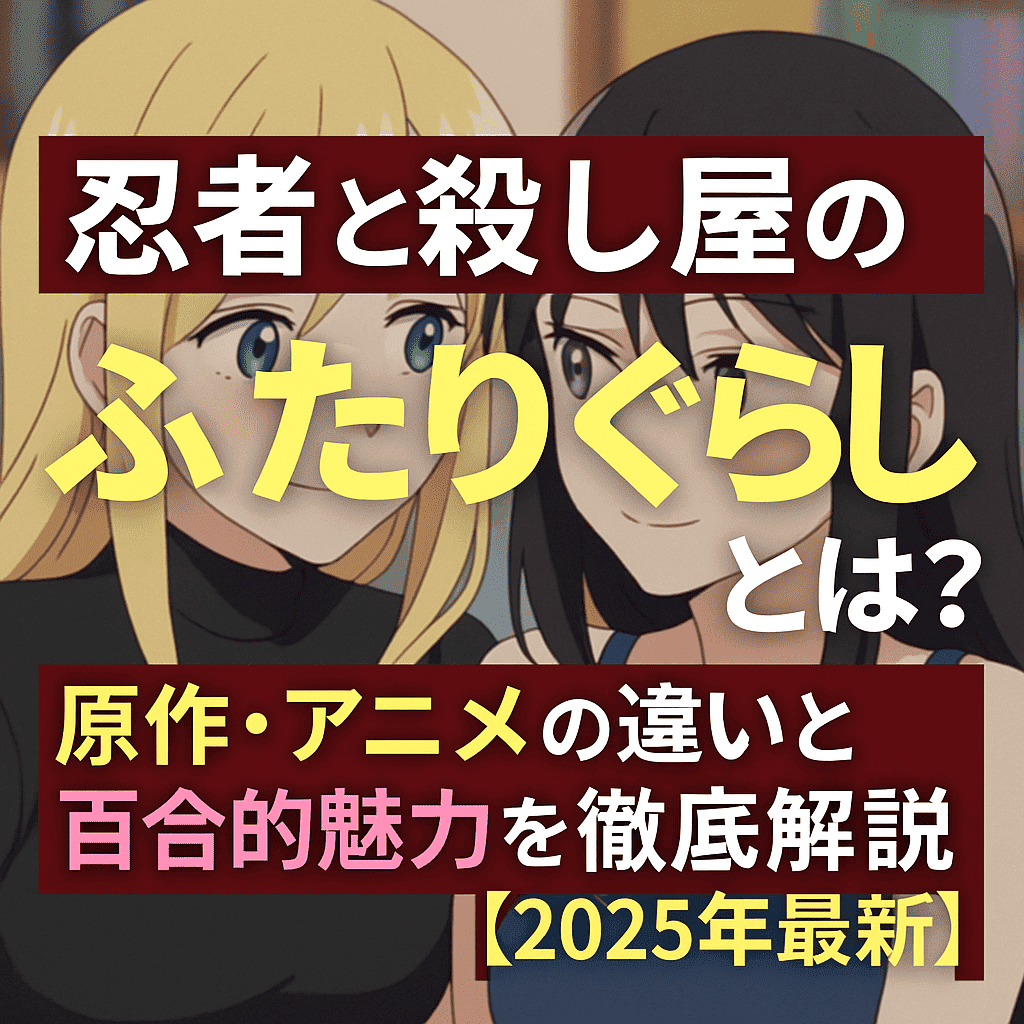
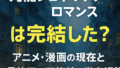

コメント