「出禁のモグラって、結局なに者なの?」──そんな疑問を抱いたあなたへ。このページでは、話題のダークファンタジー漫画『出禁のモグラ』について、キャラクターの詳細から主人公・モグラの正体、さらには『鬼灯の冷徹』との繋がりまで、徹底的に解説していきます。幻想と現実の狭間で揺れる物語の深層を、今こそ一緒に覗いてみましょう。
この記事を読むとわかること
- 出禁のモグラの世界観とキャラ設定の全体像
- モグラや浮雲の正体と“落神”に込められた意味
- 『鬼灯の冷徹』との世界観や人物造形の共通点
出禁のモグラとは?wiki風に基本情報まとめ
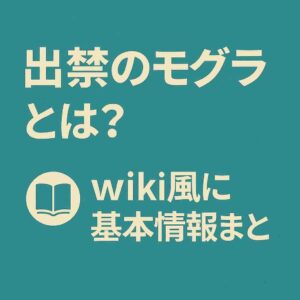
『出禁のモグラ』は、江口夏実によるダークファンタジー漫画で、2021年より講談社『モーニング』にて連載中の作品です。2025年7月にはTVアニメ化も決定しており、既にSNSを中心に大きな話題を呼んでいます。
舞台は、あの世とこの世の狭間に存在する下町のような“抽斗通り”。そこは一度死んだ霊たちが最後の灯を燃やしながら過ごす、異世界のような空間です。
主人公・百暗 桃弓木(通称モグラ)は、かつて“オオカムヅミの弓”と呼ばれた神でしたが、ある罪を犯して神籍を剥奪され、あの世への出入りを禁じられた存在=「出禁のモグラ」として、現世の“外れ”に囚われるように暮らしています。
彼の使命は、あの世に還るために必要な“灯(ともしび)”を集めること。しかし、その灯は生きる者にも癒しの力を与えてしまうため、彼は他人のためにそれを使い、結果として自身はなかなか解放されない。そこに描かれるのは、罪と赦し、孤独と連帯、そして希望の物語です。
一見ユーモラスでありながら、モグラの“出禁”という立場には、日本古来の神観や民俗学的な要素も色濃く反映されており、ただのファンタジーに留まらない深みがあります。
「なぜ彼は“神”でありながら、出禁を喰らったのか?」
「人はどこまで“他人のため”に灯を燃やせるのか?」
この物語が問いかけるのは、実はとても人間的で、切実なテーマなのです。
百暗 桃弓木(モグラ)の正体|“オオカムヅミの弓”を巡る神と罪の物語
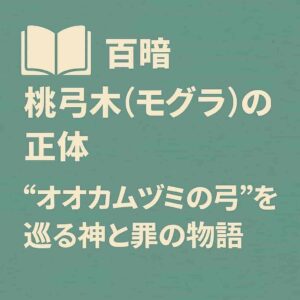
百暗 桃弓木──通称モグラ。彼はかつて“オオカムヅミの弓”と呼ばれた神であり、神聖な桃の木から生まれた存在でした。その矢は怨霊を祓い、人と神の境を守る力を持っていたといいます。
しかし、彼はある事件をきっかけに「神」の立場を剥奪され、“落神(らくじん)”と化しました。詳細はまだ物語の核心として語られていませんが、「誰かを守るために神としての掟を破った」ことが示唆されています。
この“落神”という設定は、日本神話や民間伝承における「堕ちた神=責任を取らされた神」というモチーフと重なります。神であったがゆえに、人のように泣くことも怒ることも許されなかった存在。そんな彼が、いまは湯屋の番頭として、霊たちの世話をしながら生きている──その姿に、どこか“罰を受けた者の慈しみ”が滲んでいるのです。
象徴的なのが、“灯”を巡る葛藤です。彼はこの“灯”を自らの解放のために集めなければならないにもかかわらず、他者の苦しみに出会うたびにそれを使ってしまう。まるで、自らを贖罪し続けるように。
“オオカムヅミの弓”という名は、力と責任の象徴でした。だが今の彼は、その弓を持つことすらできず、もはや矢を放つ資格もない。
──でもだからこそ、彼の言葉や行動には、神だったころにはなかった“人間らしさ”が宿っているのです。
「神でいることをやめてまで、救いたかったものは何だったのか?」
その答えを探す旅こそが、『出禁のモグラ』という物語の核心にあるように思えてなりません。
主要キャラクター紹介|浮雲・落神・他の魅力的な人物たち
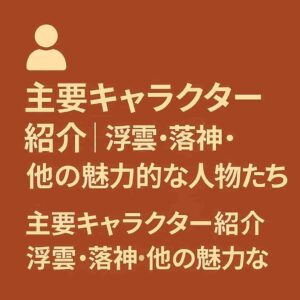
『出禁のモグラ』の魅力は、主人公・モグラだけにとどまりません。この異世界のような下町・抽斗通りには、どこか現世に未練を残した者や、神と人の狭間に生きる者たちが集まっています。その一人ひとりが、切なくて温かくて、時に自分自身の影のように感じられるのです。
◆ 浮雲(うきぐも)
抽斗通りにある駄菓子屋「ぎろちん本舗」の女将であり、モグラを“囚人様”と呼びながら監視する「看守」的な立場の女性。
彼女の存在は、ただの“監視者”では終わりません。時に優しく、時に冷徹。モグラの過去を知る唯一の人物として、彼の孤独と贖罪を黙って見つめ続けています。
見た目は飄々としていてつかみどころがないけれど、内には深い悲しみや覚悟を抱えている。その姿は、モグラ以上に“落ちた神”のようにも見えるのです。
◆ 落神(らくじん)たち
モグラのように、かつては神だったが、罪や過ちによって堕ちた存在たち。
彼らは人の姿でこの世に留まり、かつての力を持たないまま、時に人を助け、時に己の過去と向き合いながら生きています。
落神たちの描かれ方は、人間の“失敗”や“弱さ”そのもの。
「力を持っていたのに救えなかった」
「信じたものに裏切られた」
そんな想いを抱えた彼らの姿に、読者は何度も胸を突かれるでしょう。
◆ 鬼火丸(おにびまる)・独楽(こま)・その他の住人たち
霊や幽鬼の姿で登場する住人たちも、単なる“妖怪キャラ”ではなく、ひとりひとりが過去を持ち、それぞれの人生を歩んできた存在です。
中には、死んだことを受け入れられない霊や、灯を燃やし尽くすことで浄化される者もいます。
こうしたキャラクターたちとの関わりが、モグラの物語をより深く、そして人間味あるものにしているのです。
キャラクターたちは、どれも“何かを背負っている”。
それは読者が自分自身を重ねる余白でもあり、この作品の最大の強さでもあると感じます。
浮雲という存在の意味|モグラの“看守”が担う役割と過去
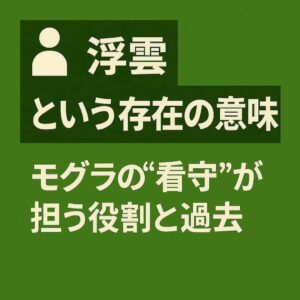
浮雲は、『出禁のモグラ』において非常に重要なキャラクターでありながら、その全貌はあえて多くを語られず、謎に包まれたまま進行します。しかし、彼女の立ち振る舞いや言葉の端々からは、モグラとの深く、そして長い因縁を感じさせるものがあります。
彼女は、表向きには“ぎろちん本舗”という駄菓子屋の女将。しかし実際には、抽斗通りという「仮の世界」に囚われたモグラの“看守”であり、唯一彼を制止したり、導いたりできる存在です。
けれど彼女は、典型的な「監視者」や「敵」ではありません。
時に厳しく、時にやさしく、どこか“母性”にも似た眼差しでモグラを見守る彼女の姿は、まるで「同じ罪を背負った者」同士のようにも見えるのです。
モグラがかつて神であったことを知っている数少ない人物であり、彼がなぜ“出禁”になったのか、その真相の一端を握っているのも彼女だと示唆されています。
──にもかかわらず、彼女は語らない。問い詰めても、笑ってごまかす。それはきっと、“語ることで壊れてしまう何か”を守っているからなのでしょう。
浮雲という名前の通り、彼女はつかみどころがなく、自由で、でもどこか哀しみを漂わせています。
彼女自身もまた、“過去に囚われた者”なのかもしれません。
「看守とは、見張る者ではなく、共に見続ける者なのかもしれない」
そんな想いを抱かせてくれるのが、浮雲というキャラクターの深さです。
落神とは何者か?──異界との接続点としての落神考察
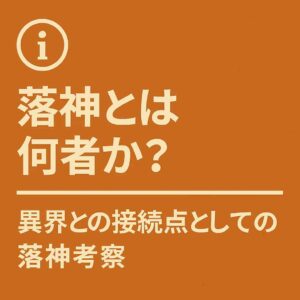
『出禁のモグラ』という物語の核には、“落神(らくじん)”という概念が横たわっています。これは単に“堕ちた神”を意味するだけでなく、人と神、現世と異界のあいだにある“接続不良”のような存在を象徴しているように感じられます。
落神とは、かつて神であった者が、罪や過失によってその神性を剥奪され、居場所を失った存在。
彼らはもう神ではないけれど、人でもない。あの世にも行けず、この世にも完全には馴染めず、ただ“灯”を燃やしながら中間地点をさまよい続ける──その姿は、まるで“生き残った魂の断片”のようです。
モグラもその一人ですが、落神たちの存在は決して例外ではなく、抽斗通りには彼らのような“宙ぶらりんの存在”がいくつも登場します。
この設定には、民俗学的な深みがあります。たとえば、日本の神話や伝承には、「役目を終えた神」や「祟り神となった神」が数多く存在します。
それは決して“悪”ではなく、「忘れられた者」「感情を持ったがゆえに失墜した者」として、語られることもしばしばです。
『出禁のモグラ』が描く落神たちは、まさにその“語られなかった物語”を生きる者たちです。
彼らは弱さを持ち、罪を悔い、時に人のために灯を分け与える──その姿に、どこか「自分にも思い当たる節」があると感じる人も多いのではないでしょうか。
「強くあろうとしたのに、守れなかった」
「間違いだと分かっていたけれど、止まれなかった」
落神という言葉は、単なるファンタジーの設定を越えて、現代を生きる私たちの“心の構造”そのものに触れてくるのです。
“鬼灯の冷徹”との繋がりを探る|江口夏実作品に共通する世界観と人物像
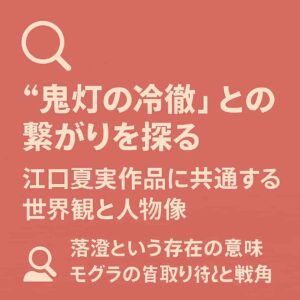
『出禁のモグラ』が連載され始めた当初から、江口夏実の前作『鬼灯の冷徹』との“世界観の繋がり”を感じ取った読者は少なくありません。
舞台が“あの世”に近い領域であること。
死者や霊、神々が人間的な悩みや感情を抱えながら描かれること。
そして、主人公が「人であって人でない存在」として、人間社会の歪みや悲しみを受け止め続けること。
これらの要素は、まさに『鬼灯の冷徹』から受け継がれた江口作品特有の語り口といえるでしょう。
たとえば、鬼灯は閻魔大王の補佐官として冷徹に地獄を仕切る存在でしたが、その根底には「人間の愚かしさに深く共感しながらも、正す」という強い信念がありました。
一方、モグラはその“共感”に囚われてしまったような存在。他人の痛みに寄り添いすぎるあまり、自分を解放できない。
鬼灯が「ルールと正義」の側に立っていたとすれば、モグラは「赦しと迷い」の側に立っているのです。
また、両作品のキャラクターデザインにも共通点があります。
とくに“浮雲”というキャラクターは、鬼灯と同じく黒髪・切れ長の目・静かな威圧感を備えており、ファンの間では「女性版鬼灯」とも言われています。
世界観においても、“地獄”という秩序だった死後の世界を描いた『鬼灯の冷徹』に対し、『出禁のモグラ』では“死に切れなかった者たちの余白”が舞台となっており、同じ死後の物語でもその視点はまったく異なります。
それでもどこか、「あのキャラクターたちが、この世界のどこかでまだ生きているのではないか」と思わせてくれるのは、江口夏実という作家が持つ、独特の“異界の温度”によるものなのでしょう。
『鬼灯の冷徹』が好きだった読者にとって、『出禁のモグラ』はまさに“続編ではないのに続いている物語”として、強く心に残る作品です。
まとめ:出禁のモグラが描く「現代神話」とは何か
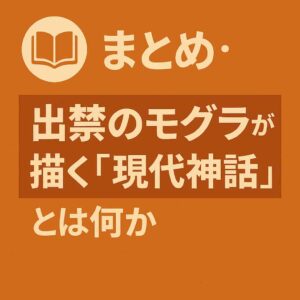
『出禁のモグラ』は、“神”という存在を単なる超常的な存在としてではなく、「罪を抱えた誰か」「かつて力を持ちながらも堕ちた者」として描いています。
それはまるで、私たちが日々の中で感じる“後悔”や“贖罪”、そして“報われない優しさ”そのものを神話にして見せてくれているようです。
モグラは、かつて神でありながら人のように迷い、失い、そしてそれでも他者のために灯を使い続ける。
浮雲は、看守でありながらも、彼の過去を一緒に背負う“共犯者”のような存在として寄り添う。
彼らが生きる“抽斗通り”は、どこかこの社会そのもののメタファーにも見えます。
人と人のあいだに生まれる誤解、許されない過去、それでもなお灯し続けたい誰かへの思い。
だからこそ、この作品は読むたびに、私たちに問いを投げかけてくるのです。
──あなたは、誰かのために自分の灯を差し出せますか?
──“出禁”になってもなお守りたいものは、あなたにありますか?
『出禁のモグラ』は、幽霊や神を描きながら、もっとも人間らしい物語を紡いでいます。
それはきっと、現代という“答えの出にくい時代”に生きる私たちが必要としている、もうひとつの神話──つまり、“現代神話”なのです。
この記事のまとめ
- 「出禁のモグラ」の基本設定と世界観の紹介
- 主人公・百暗桃弓木の正体と過去に迫る
- 浮雲や落神など重要キャラの役割を解説
- “灯”を巡る葛藤と贖罪のテーマに注目
- 鬼灯の冷徹との繋がりや作風の共通点
- 現代神話として読む新たな解釈の提示
アニメ『出禁のモグラ』を観るなら、独占先行配信中のDMM TVで。
今なら、14日間の無料トライアルが実施中。さらに話題の『薬屋のひとりごと』『怪獣8号』『ダンダダン』『盾の勇者の成り上がり』など、人気アニメも見放題で楽しめます。
DMM TVは、
「非常識コスパ」と評されるほどの充実ぶり。
『出禁のモグラ』を皮切りに、あなたの“アニメ視聴体験”がきっと変わります。
▼ 今すぐ無料でチェック
👉 DMM TVで『出禁のモグラ』を観る(14日間無料)

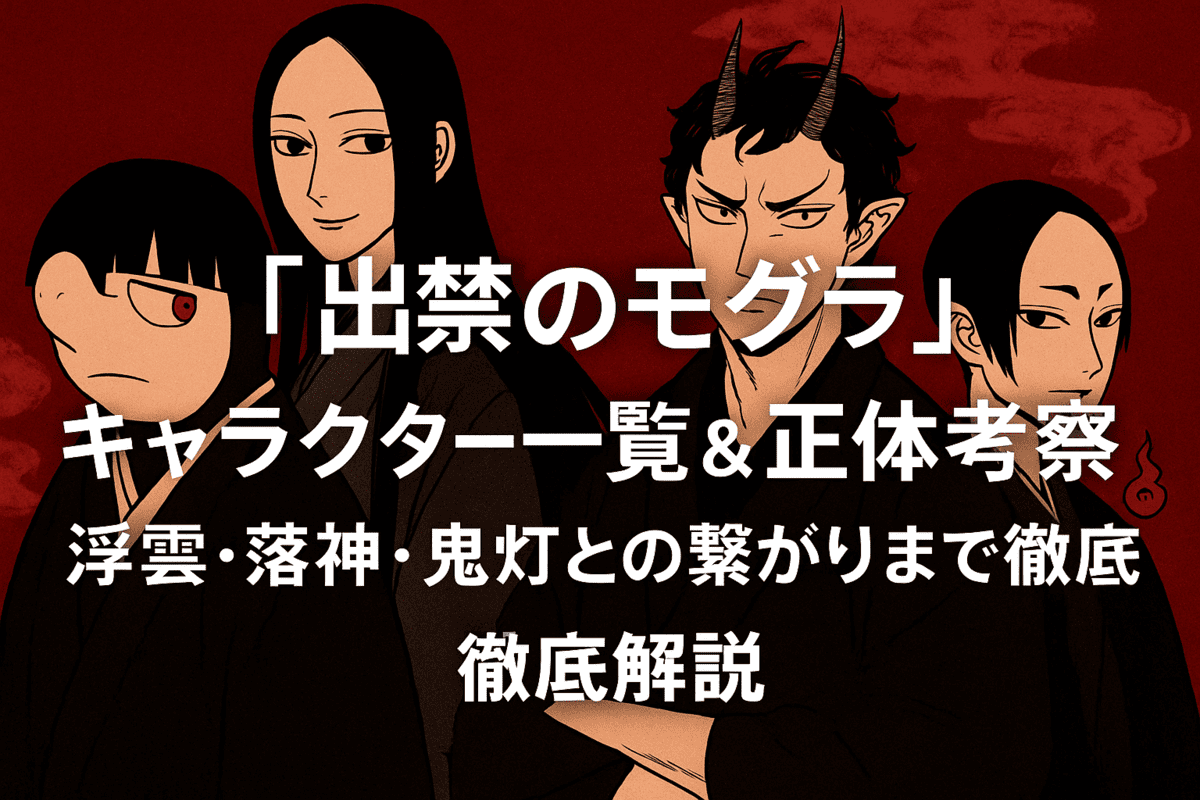
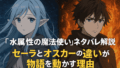
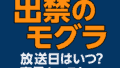
コメント