アニメ化が決定し注目を集めるバトル漫画『ガチアクタ』。ネット上では「炎炎ノ消防隊に似てる」「チェンソーマンっぽい」といった声も見られます。果たしてこれはオマージュなのか、それとも偶然の一致か?この記事では、『ガチアクタ』と『炎炎ノ消防隊』『チェンソーマン』の共通点と違いを徹底比較しながら、作品ごとのオリジナリティを掘り下げていきます。
この記事を読むとわかること
- 『ガチアクタ』と『炎炎ノ消防隊』の共通点と違い
- 『チェンソーマン』との作風・主人公像の類似点
- “似ている”という声への考察と作品のオリジナリティ
『ガチアクタ』と『炎炎ノ消防隊』の共通点とは?作画・テーマ・演出を比較
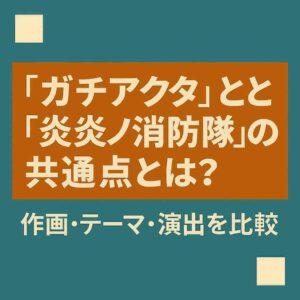
『ガチアクタ』を語るとき、よく比較されるのが『炎炎ノ消防隊』です。
実は、ガチアクタの作者・裏那圭(うらな けい)氏は『炎炎ノ消防隊』の作者・大久保篤氏の元でアシスタントをしていた経歴を持ちます。
この事実が、両作の“似ている”という印象の一因となっているのは確かでしょう。
では具体的に、何が「似ている」と感じられるのか──以下に主な共通点をまとめてみます。
- ダイナミックな作画とエフェクト表現:
両作ともに、バトルシーンの“火花のような演出”やスピード感が印象的で、キャラクターの動きに熱量があります。 - “下層社会”を舞台にしたダークな世界観:
『炎炎』は超常災害による崩壊した世界での「消防隊」、
『ガチアクタ』はゴミと犯罪者の子孫が捨てられる「奈落の世界」──いずれも社会の裏側に生きる者たちの視点が描かれています。 - “信じるもの”への戦い:
シンラは母や家族への信念、ルドは“汚名を背負った者”としての自分自身を信じて戦います。
両者ともに、信念が物語の核になっている点も共通しています。
ただし、似ているのは“スタート地点”だけかもしれません。
『ガチアクタ』はより社会派でリアルな「差別・排除」の問題を掘り下げており、人間の孤独や痛みを内面から描くドラマ性がより色濃くなっています。
この点で、『炎炎』よりも“重く尖った方向性”にシフトしているのが特徴です。
つまり、作画の迫力や世界観の構造に影響は感じられるが、物語の核心は別方向を向いている。
アシスタント時代の経験を糧に、“自分にしか描けない物語”を構築していく過程──それこそが、『ガチアクタ』の醍醐味なのかもしれません。
『チェンソーマン』との類似点は?世界観・主人公像・暴力描写から分析
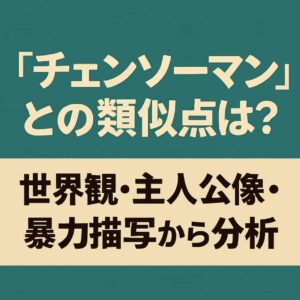
『ガチアクタ』と『チェンソーマン』。
両者の直接的な繋がりはないものの、「似ている」と感じる読者が一定数いるのも事実です。
それは、現代の少年漫画が共有する“過激さ”と“切実さ”の両立という傾向に深く関係しています。
まず、視覚的な印象として共通するのは、暴力描写の生々しさと、演出のスピード感。
チェンソーマンの藤本タツキ作品に見られる“衝撃的なカット”や“突発的な死”の演出は、読者の感情を揺さぶる強烈な仕掛けです。
『ガチアクタ』もまた、キャラクターがあっけなく倒れる緊張感や、「倫理」よりも「生存」が優先される世界観において、読者の想像を裏切る描写が随所にあります。
また、主人公像にも共通項が見られます。
『チェンソーマン』のデンジは、「普通の生活がしたい」という過剰なまでに個人的な欲望から戦う存在。
一方、ルドは「犯罪者の子孫」という社会的なレッテルを背負いながら、自分が生きている意味を模索しています。
どちらも“正義”ではなく、“個人の生”をモチベーションに行動する異色の主人公なのです。
さらに、世界観の荒廃性や倫理観の崩壊具合も共通しています。
「普通の人がいない」「まともが通じない」──そんな世界のなかで、どれだけ不完全なまま“信じたいもの”を守るかが物語の芯になっている点は、まさに今の時代に響くテーマだと言えるでしょう。
とはいえ、『チェンソーマン』が暴力とユーモアの狭間で物語を疾走する“カオスな自由”の物語だとすれば、
『ガチアクタ』は、もっと粘り気のある“現実との格闘”の物語です。
同じく刺激的で尖った漫画でありながら、感情の焦点の置き方に違いがある──それが両者の個性と言えるでしょう。
裏那圭と大久保篤・藤本タツキ──作家性とアシスタント経歴の関係性
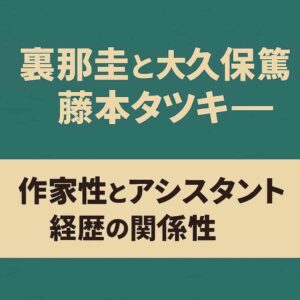
『ガチアクタ』の作者・裏那圭(うらな けい)は、プロデビュー前に『炎炎ノ消防隊』の大久保篤氏の元でアシスタントとして経験を積んだことが知られています。
一方、『チェンソーマン』の藤本タツキとは直接的な繋がりはありませんが、作家性の比較として並べられることも少なくありません。
まず、大久保篤との関係性において特筆すべきは、“描線のエネルギー”です。
裏那氏の絵には、大久保作品にも通じる線の暴れ方、アクションの流動性が見受けられ、
「教わった技術を、さらに自分の感情にフィットさせて進化させた」という印象があります。
ただし、描くテーマの深さや方向性には大きな違いがあります。
大久保作品が“個人の信仰や家族”を軸にした物語を構築してきたのに対し、
裏那圭は社会構造・階級・差別といった現実的テーマにフォーカスし、それを漫画という媒体で描こうとしているのです。
藤本タツキとの比較では、直接的な師弟関係こそありませんが、“現代的な作家性”という意味で共通点があります。
たとえば、物語を通して「正しさ」を押し付けない姿勢や、キャラの矛盾や弱さを包み隠さず描くところは、両者に共通する現代的な倫理観とも言えます。
どちらの作家も、「漫画だからこそ届く感情表現」を探求しており、
裏那圭もその系譜の中で、“自分にしか描けない物語”を模索している段階にあるのでしょう。
アシスタント経験は“影響”の源ではあっても、“模倣”の証ではない。
むしろ、そこからいかに“自分だけの声”を探すかが、今の裏那圭の挑戦なのだと思います。
「似てる」は悪か?ジャンルの中で光る『ガチアクタ』の個性とは
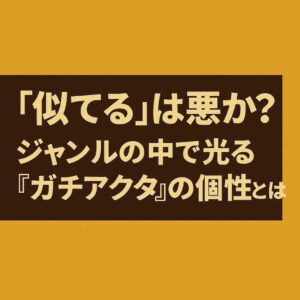
「この漫画、どこかで見たことある」「あの作品っぽい」──そんな感想は、SNSでもよく見かける言葉です。
『ガチアクタ』も例外ではなく、『炎炎ノ消防隊』や『チェンソーマン』と似ていると語られることがあります。
でも、果たして「似てる」という評価は、ネガティブなものなのでしょうか?
マンガというジャンルには、それぞれの“文法”があります。
バトル漫画であれば「力と信念の衝突」、ダークファンタジーなら「破滅的な世界と再生への願い」──
そうした枠組みのなかで作品が「似る」のは、むしろ共通言語としての強みであり、その中でどこまで個を打ち出せるかが真の勝負なのです。
『ガチアクタ』が光るのは、まさにその“個性の彫りの深さ”にあります。
ゴミと犯罪者のレッテルを背負った少年たちが、生きる意味を探して抗う物語。
その描写には、怒り・喪失・孤独・希望──あらゆる感情の“におい”が宿っている。
暴力的な描写や退廃的な世界観があっても、それは単なる演出ではなく、“現実のしんどさ”をフィクションに置き換えた、切実な声。
その誠実さが、『ガチアクタ』を“似ている”では終わらせない理由なのです。
ジャンル内で共通点があることは、むしろ読者に「取っつきやすさ」を与えます。
そして、読んだあとに残る“感情の余韻”こそが、その作品だけが持つ個性であり価値。
『ガチアクタ』はまさにそんな、“ジャンルの中で自分だけの色を放つ”漫画。
だから僕は、「似てるね」と言われても、「でも、それ以上に“痛かった”よ」と返したくなるのです。
まとめ:影響を超えて“自分の物語”を描く『ガチアクタ』
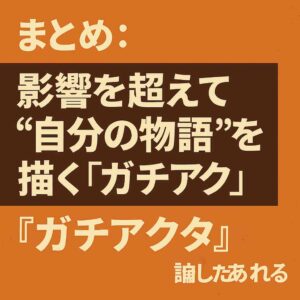
『ガチアクタ』は、『炎炎ノ消防隊』や『チェンソーマン』といった作品との比較にさらされながらも、明確に“自分だけの物語”を描こうとしている漫画です。
確かに、作画や演出、テーマ構造には共通点も見られます。
でもそれは、“影響を受けた”というより、“そこから自分だけの問いを見つけた”というプロセスの証に感じられるのです。
ルドという少年を通して描かれるのは、社会の中で見捨てられた人間が、それでも「信じたいもの」を選び取っていく過程。
それは、大久保篤や藤本タツキとは異なる、裏那圭自身の言葉でしか描けない主題です。
「似てる」という評価の先にあるのは、“誰かの痛みに寄り添う力”だと僕は思います。
そして、『ガチアクタ』はその痛みと真正面から向き合うことで、確かに“唯一無二”の物語を紡いでいる。
ジャンルや技術を超えて、フィクションが人の心を動かすとしたら──
それは、「本気で描かれた言葉」だけが持つ力なのではないでしょうか。
『ガチアクタ』は今まさに、その道の途中にあります。
誰かの声に似ているかもしれない。それでも、その声でしか届かない感情がある。
僕たちは、そんな物語の“成長”をリアルタイムで見守っているのかもしれません。
この記事のまとめ
- 『ガチアクタ』は『炎炎ノ消防隊』と世界観や作画に共通点あり
- 『チェンソーマン』とは主人公像や暴力描写で類似点がある
- 裏那圭は影響を受けつつも独自のテーマを追求している
- ジャンルの中で“似ている”は創作の自然なプロセス
- 『ガチアクタ』は今、自分の物語を描こうとする成長中の作品

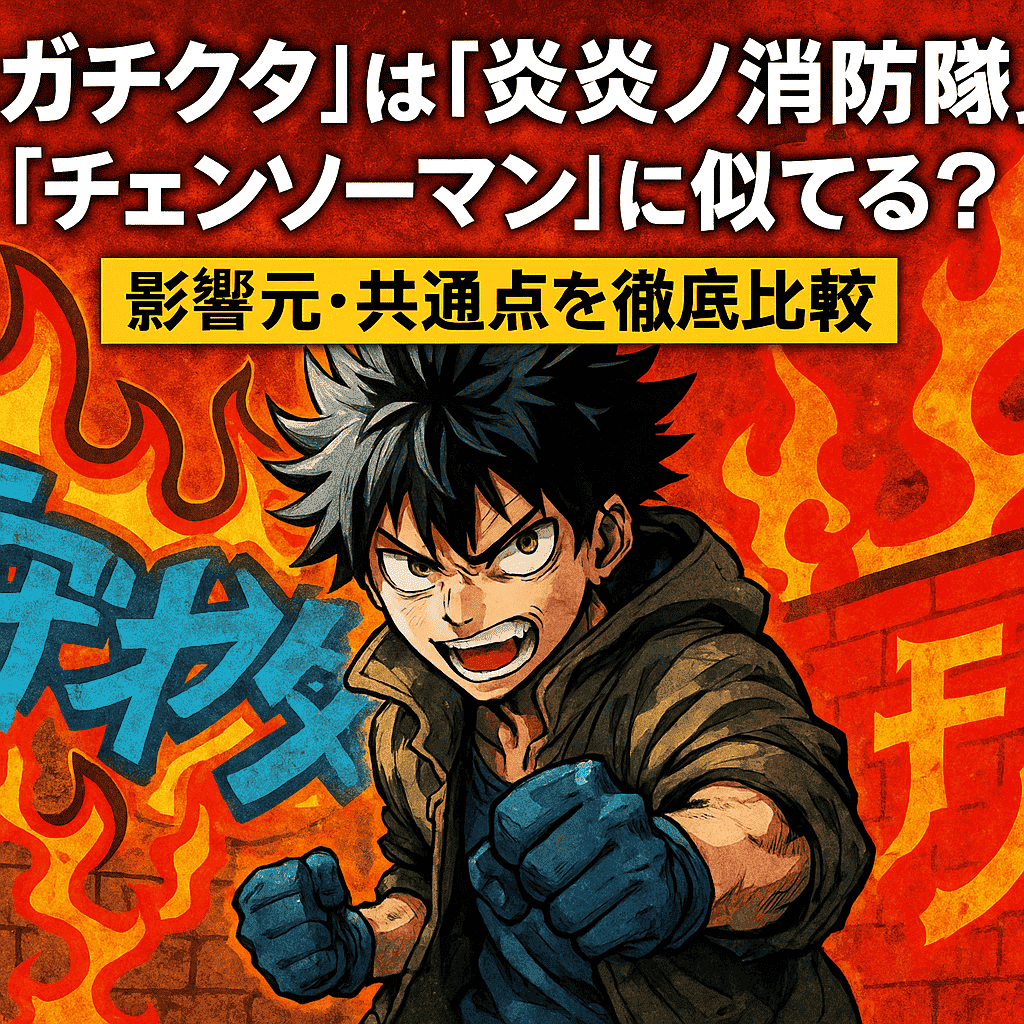
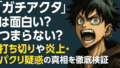

コメント