「この歌声、どこかで聴いた気がする」──。
ふとした瞬間に、記憶の奥に灯るような感覚がある。
それが『うたごえはミルフィーユ』というプロジェクトに出会ったとき、静かに確信に変わったんです。
“アカペラ×キャラクター”という挑戦のなかで、彼女たちはハモネプへ、アニサマへ、そして“ウマ娘”という別の舞台へと歩みを広げていきました。
だけどこれは単なる声優活動でも、CD売上でもない。
「歌うこと」を通して、彼女たちの“現在地”を私たちに教えてくれる。そんな連なりの物語です。
■ うたごえはミルフィーユとは? アイドルでもアニソンでもない“第三の声”
たとえば、アニメに出てくるキャラクターが「歌を歌う」と聞いて、どんなものを想像しますか?
キラキラした衣装をまとったアイドル? 大きなステージで盛り上がるアニソンライブ?
『うたごえはミルフィーユ』は、そのどちらとも、ちょっと違います。
このプロジェクトは、6人の声優が「アカペラだけで歌を届ける」ことに挑戦しています。
つまり、楽器は一切なし。あるのは“声”だけ。
リードボーカルも、ハーモニーも、リズムも、ぜんぶ自分たちの声でつくりあげる。
しかも、それをキャラクターとしてやりきるんです。
アイドルのように輝きながら、アニソンのように世界観を持ち、
でもそのどちらにも属さない、“第三の音楽”とも呼べる存在。
それが『うたごえはミルフィーユ』なんです。
たぶんこれは、「声の力だけで、どこまで届くのか」を証明しようとする、
少し静かで、でもすごく強い挑戦だと思います。
■ ハモネプ出演で証明された「生の声」だけの実力
2024年3月、フジテレビ系の人気番組『全国ハモネプ大リーグ』に、声優だけで構成されたユニットとして『うたごえはミルフィーユ』のメンバーが出演しました。
アニメのキャラクターとしてではなく、“中の人”である声優自身が、生放送のステージに立ち、
楽器を一切使わずに、アカペラだけでYOASOBIの「アイドル」を披露したのです。
この挑戦は、ある意味とても危ういものでした。
なぜなら、「声優が歌う=キャラ人気頼み」と思われがちな中で、
キャラではなく“声だけ”で勝負する場だったからです。
けれど彼女たちは、見事にそれをやってのけました。
一糸乱れぬハーモニー、息を飲むようなボイスパーカッション、
そしてキャラクターを離れてもなお伝わる“物語性”。
そのすべてが、視聴者の心を静かに打ち抜きました。
このステージで証明されたのは、「うたごえはミルフィーユは、声優ユニットである前に、音楽ユニットである」ということ。
それは、アニメという“架空の世界”から飛び出しても、なお届く声だったということです。
■ アニサマ2024での共演──“アカペラ”が照らす声優の未来
2024年8月、さいたまスーパーアリーナ。
アニメソングの最大級イベント『Animelo Summer Live(アニサマ)』のステージに、『うたごえはミルフィーユ』のメンバーが登場しました。
共演したのは、声優アーティスト・東山奈央さん。
そして披露されたのは、『カードキャプターさくら』の名曲「プラチナ」。
でもこの日、その曲は“全編アカペラ”で歌われたのです。
何万人という観客が見守るなか、声だけで組み上げた世界。
楽器がなくても、光もなくても、
音だけで胸を打てるということを、彼女たちは証明しました。
アニサマという場は、ただのライブではありません。
アニメ音楽の「今」と「これから」を見せる舞台です。
そこで“アカペラ”という選択肢を提示したことは、
「これが次の声優表現の形かもしれない」──そう感じさせる瞬間でもありました。
アニメの中だけでは伝えきれない“声の奥行き”を、
現実のステージで照らし出した時間。
きっとこの日から、『うたミル』は「ただのアニメ」ではなくなったんだと思います。
■ ハロプロイズムを受け継いだ構成力と表現力
『うたごえはミルフィーユ』を聴いていると、どこかで感じたことのある“緻密なハーモニー”や“感情の込め方”に気づくことがあります。
それは、たぶんハロプロ的な表現力をどこかで受け継いでいるからだと思います。
ハロプロ(モーニング娘。や°C-uteなど)は、ただ可愛いだけのアイドルではありません。
1音1音の強弱やリズムの抜き差し、メンバーごとの声質の生かし方──
「グループ全体でどう伝えるか」にとても意識的なユニットでした。
『うたミル』にも、そのエッセンスが確かにあります。
楽器がないぶん、声の重ね方ひとつで印象が変わる。
誰がリードを取るのか、誰が支えるのか、その構成力のバランス感覚に、ハロプロ的な“聴かせ方の設計”を感じます。
さらに、出演声優の中には実際にハロプロ楽曲をアカペラでカバーしている人たちもいます。
その経験が、ただの「演技の延長」ではない、“歌で伝える”という芯の部分に繋がっている気がします。
『うたミル』が届けるのは、アニメキャラの歌ではありません。
声の中に感情があり、構成の中に意図がある。
そこには、アイドルという枠を超えた“職人のような”表現があります。
■ ウマ娘との“声優クロス”──キャラクターを超えて響くもの
『うたごえはミルフィーユ』のメンバーの中には、『ウマ娘 プリティーダービー』にも出演している声優がいます。
たとえば、花井美春さん(ツインターボ役)、夏吉ゆうこさん(メジロアルダン役)、須藤叶希さん(ワンダーアキュート役)──
どの方も、“声”でキャラクターに命を吹き込むプロフェッショナルです。
でも興味深いのは、「別作品に出ている=売れている」という話ではありません。
むしろ、ひとりの声優が違うキャラクターをどう演じ分けているかを知ることで、
『うたミル』のキャラたちが、より生き生きと見えてくるんです。
たとえば『ウマ娘』で力強く走る彼女が、『うたミル』では繊細なハーモニーを支える。
同じ声なのに、まるで違う心で語りかけてくる。
そのとき、キャラの声ではなく、“この人の声”を聴いていたんだと気づかされます。
声優を起点に複数の作品がつながる現象を、「声優クロス」と呼ぶ人もいます。
そのクロスは、単なる出演履歴ではなく、「誰かの記憶に、何通りもの温度で届く」という証拠なのかもしれません。
だからこそ、『うたミル』はただのアニメじゃなくなる。
あなたが『ウマ娘』を愛したその声が、今度は別の物語で、別の形で、また心に触れてくる。
それがきっと、“キャラクターを超えて響く”ということなんだと思います。
■ たぶんこれは、“成長を信じる”ためのコンテンツだ
『うたごえはミルフィーユ』を聴いていると、
「あ、この子たちはまだ“途中”なんだな」と感じる瞬間があります。
完璧じゃないハーモニー。
ちょっと揺れる音程。
でもそのすべてが、「今この瞬間しか聴けない声」として届いてくる。
このプロジェクトがすごいのは、最初から完成されたものを見せていないことだと思います。
アニメで描かれるキャラクターたちも、現実の声優たちも、
「練習して、ぶつかって、少しずつできるようになっていく」その過程が重ねられている。
だから見ているこっちも、“信じる”という立場を求められる。
「まだ未完成だけど、きっと良くなる」
「まだ知らないけど、きっと好きになる」
──そんな気持ちで作品と向き合っている自分に、ふと気づくんです。
『うたミル』は、たぶんそういうコンテンツです。
「応援」じゃなくて、「信じる」もの。
今の声を聴いて、これからの音を楽しみにできる、そんな稀有な場所なんだと思います。
■ まとめ|このプロジェクトが、なぜ記憶に残るのか
『うたごえはミルフィーユ』は、たくさんの「声」でできています。
それはキャラクターの声であり、アカペラのハーモニーであり、
そして、まだ不確かだけど確かに育っていく“何か”の声です。
アニメで描かれる物語。
ハモネプで見せた挑戦。
アニサマで聴かせた景色。
そして、ファン一人ひとりが持っている「この声、どこかで聴いたことがある」という記憶。
それらが重なったとき、ただのアニメではない“ひとつの軌跡”として、心に残るんだと思います。
キャラクターでも、アイドルでも、声優でもなく──
“そのあいだ”を生きている声たち。
『うたごえはミルフィーユ』は、それをまっすぐに届けてくれる作品です。
だからきっと、いつか思い出すときも「この名前を忘れたくない」と思える。
そんな風に、静かに記憶に刻まれていくんじゃないでしょうか。


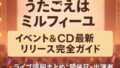

コメント